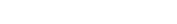Hong Kong eyes 2024 turnaround amid strong headwinds
With the SAR failing to meet its GDP goal for 2023 amid a placid IPO and property market, FinanceAsia looks at the challenges and opportunities for the city.
December 19, 2023




.png&h=171&w=304&q=75&v=f99a4c25f0&c=1)




.jpg&h=171&w=304&q=75&v=f99a4c25f0&c=1)